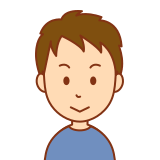
DIYを始めたいんだけど、何の道具があればいいのかわからない。
今日はこんな疑問に答えていきます。
✔ 本記事の内容
- 揃えたい手道具
- 道具の使い方
- 精度とスピードが上がる電動工具
まずは作りたい物の出来上がりのイメージを軽く思い浮かべよう。大工歴25年なので信憑性はあるかと思います。
手道具

絶対に使うもの
- 鉛筆(2H)
- 指矩(さしがね)
- 巻き尺(メジャー)
- 玄能(げんのう)
- 手鋸(てのこ)
- 手回し(ドライバー)
最低限のこれらの道具を使っていきます。
鉛筆

大工おすすめ鉛筆は、『三菱鉛筆 ユニ鉛筆 2H』です。これで間違いないです。自分は12本入りを25年間ずっとお世話になっております。単品(1本)
もあります。
鉛筆の芯の硬さがなぜ2Hなのかというと、多少凹凸のある材料でも芯が折れずらく墨入れできるからです。墨入れというのは材料に鉛筆、または「墨刺し」(すみさし)でしるしをつけることです。
DIYでは「墨刺し」は使わないほうがいいです。主に家を組み立てるすべての木材(構造材)に墨(墨汁)を付けて、しるしをつけるために使う竹でできた鉛筆みたいなものです。このことを大工用語で「墨付け」といいます。「墨刺し」で間違えて線をひいてしまった場合、消すためには「鉋」(かんな)で墨が消えるまで削る羽目になるので、コンマ何ミリ材料が薄くなるのと単純にめんどい、消しゴム最高!
2Hの鉛筆には折れにくいのと、もうひとつ利点があります。なにかというと薄くしるしをつけることができ、最終的に塗装するときにしるしが見えなくなるからです。ただし芯自体は固いので木材に傷をつけるくらい力を入れてしるしをしてはいけません。これは基本中の基本です。材料にはやさしく薄く墨付けしよう。
鉛筆は鑿(のみ)で研ぎます。その鑿が切れないと綺麗に先端まで研げません。それが見つかると怒られます。そして仕事が終わってから地獄の鑿研ぎが待ってます。今思うと、刃物は常に切れるようにしておけって教えだと思います。もちろんそんなことを一言も教えてくれません。見て覚えろの世界です。
指矩(さしがね)

大工おすすめ指矩のメーカーは『シンワ 曲尺 名作 50㎝』です。これで決まりです。これのセンチ目盛りのやつがいいです。間違っても尺目盛りを買わないでください。いまどき「尺貫法」を使っているのは材木製材所くらいです。自分は職業柄、尺のほうがすぐわかりますけど。ちなみに自分の身長は六尺六厘(182㎝)で、足のサイズは九寸二分四厘(28㎝)です。笑
指矩が無ければ始まらないってくらい必須アイテムです。実際に誰かが自分にあるものを作ってと頼まれて、指矩がなければやる気度数が0.1まで下がります。それくらい大事です。指矩は直線をひくのと長さをはかるためだけではなくて、もっと大事な役割があるんです。それは直角を出すことです。大工用語では「矩」(かね)を出すと言います。
この直角がなければ歪んだ代物の出来上がりです。出来上がった感想は「ただただ恥ずかしい」ってことになります。指矩は薄ければ薄いほど扱いやすいですが、押さえ方によって引く線がくるいやすくなります。薄くなると押さえたときに尻(長いほうの先端)が跳ね上がりがちですが、材料にきちんとなじませましょう。
また指矩は落とすとくるいやすく、矩を正確に出せなくなります。確かめる方法は、材料の直線部分に長いほうを当てて直角に伸びてる短いほうに沿って線を引き、その線を引いたほう(普通は短いほう)の反対側にまた長いほうを材料の同じ直線部分に当てて、指矩の短いほうを線に当て、その線が指矩と一致していればくるっていないことになります。基本は利き手じゃないほうで長いほうを持ちます。
落としたり、間違えると指矩の長いほうで叩かれた記憶があります。その当時は正確な使い方を覚えるというより、叩かれないために覚えようって時代でした。それに道具の名前や使い方は一斉教えてくれません。なので怒られっぱなしで叩かれっぱなしでした。笑
メジャー

大工用語では「スケール」って呼んでます。大工おすすめスケールは、『TAJIMA ハイ 25mm×5.5m スケール 』の幅25㎜×長さ5.5mの黄色いやつです。今はロックストッパー付きですが、こんなの大工からすれば指で押さえるので邪魔なだけで、ロックなんていりませんしロックなんて使ったことないです。
古い金物屋とかにはロック無しが置いてあるかもしれませんけど、あんまりないので仕方なく使ったりします。黄色い「トゥルン」としてるやつです。これも間違わずに「メートル目盛り」を買いましょう。
水(雨)に濡らすと水が中に入り込んでスムーズに使えなくなるだけでなく、途中でちぎれたりして使い物にならなくなります。先端の0目盛りが巻いた時のストッパーになってるので、中のバネがおとなしくなるまで巻き続けてちぎれた先端も中にインして二度とはかれなくなります。濡れた時には、5.5m全部引き出して綺麗に水気を拭き取りましょう。安くないのに、これで何度おしゃかにして絶叫したことか。笑
あと、目盛りの先端の銀色のL字の金物がカタカタ動くのは理由があって、引っかけて測ると1㎜伸びて金物の内側が0になります。そして押し付けて測ると金物の外側が0になります。そのため金物の厚さは1㎜で、動くようになってます。なので買うときは先端の金物がすこしでも曲がっているものは買ってはいけません。だれかが落としたかなにかで正確に測れないので曲がってないスケールを買いましょう。
自分は落として曲げたときは、平らな石の上で玄能で叩いて直して使ってました。うまく叩くと治ります。曲がったのを叩いて直すだけで、つぶしてしまうとアウトです。力加減が難しく、へたこくとつぶれて絶叫です。
玄能(げんのう)

金槌(かなづち)のことです。玄能にはいくつか種類がありますが、特に大工がおすすめするメーカーなどはないです。形は片口が一般的で、片方が平らで、もう片方が尖ってるよく見る形のやつです。ステン製のものを自分は使っていますが鉄よりちょっとお値段がお高くなってます。
玄能は折るとかなり面倒なことになりますので注意しましょう。ホームセンターへ行って、玄能の柄だけを買ってきて頭に刺さってる柄を錐(きり)で砕いて抜いてから、買ってきた柄の差し込み部分を水で濡らし削って仕込んで頭を少し出して小口を叩いて伸ばして抜けなくしてから楔(くさび)をさします。かなり面倒なので折らないほうがいいです。誰かに頼まれたら「嫌です」って即答できるレベルの面倒くささです。笑
個人的に玄能は重いほうがいいです。釘を狙うときのスイングがブレにくいです。今は軍手をしてますが、昔は素手の作業だったので指を打てば泣きそうです。爪を叩いて中に血豆ができてかなりの期間その血豆との共同生活が始まります。血豆が先端に来てなくなるまで相当の期間がかかります。そして普通に恥ずかしいです。ちゃんと狙いましょう。笑
手鋸(てのこ)

のこぎりも特に大工おすすめメーカーはないのですが、品名が『Z ゼットソー 265』っていうやつが使いやすいです。刃は「横挽き刃」でこの手鋸は木目に直角、または斜めに切断するときに使います。鋸の刃には「横挽き刃」と「縦挽き刃」があります。これを間違えて使うと切断に時間がかかったり、切った小口がきれいになりません。
「縦挽き刃」は木目と平行に切断する鋸のことを言います。大工さんののこぎりで想像するのは両側に刃の付いた縦長の のこぎりを思い浮かべるとおもうのですが、それが大工用語でいう「尺鋸」と言って刃の長さが約30㎝の両刃鋸で、片方が「横挽き刃」でもう片方が「縦挽き刃」両方に刃のついたのこぎりです。今はホームセンターで本物の尺鋸はあんまり見かけませんが、金物屋には置いてますね。むかしは鋸の刃も研いで使っていました。地獄。
手鋸をうまく挽くコツは握ったときに小指に一番力を入れて握って挽いて、親指を刃先に向けて引く時だけ力を入れます。日本はそういう刃の仕組みになっています。包丁とか刀もそうですが引いて切るイメージです。外国は押して切る刃の仕組みになっているところもあります。なので日本では押すときは力を入れず押してるだけです。中国も引き鋸だったと思います。
手鋸で怪我をするとカッターと違い、痛みがずっと続きますので気を付けましょう。また慣れないうちは必ず軍手をつけてから作業にあたりましょう。心配な方はあまりグリップしませんが革手でもいいです。刃物を扱うときには十分注意しましょう。
手回し(ドライバー)

これに関してはおすすめもくそもありません。というか昔は手回しだったってだけで、ドライバーなんて使っていたら日が暮れてしまいますし、腕がパンパンになって熱くなります。そして箸を持つ手が震えます。なのでここでは電動工具になりますので、あとでご説明します。電動ドライバー考えた人マジで神!自分はこれを使ってます。
自分が弟子入りしたときにはすでに、充電式電動ドライバーはありました。なのになんで手回し使わせる?イジメとか?っておもいましたが、今思うと、ネジの本質を知るためだったんです。手回しでうまくねじ込み出来ない人は電動ドライバーを使っても、折ったり、なめったりしてうまく使えない人を見かけます。
ネジ(うちらはビスって呼んでます)をうまくねじ込むには、材料に対して垂直でねじ込む方向に押し付けながら回し、ネジの先と手に力を入れる点が一直線にならないとうまくねじ込めません。それは手回しで何本もねじ込むと自然と体が覚えます。なので初めて電動ドライバーを使う場合は軽く押しながら締め付けるとスムーズに入ってくれます。慣れてきたら押す力をすこしずつ強めるといいでしょう。
使い方
- 鉛筆は可能な限り尖らせて落とさない事。2Hは芯が硬いため落とすと中で芯が折れます。そうなると研ぐたびに中で折れている芯がポロポロ落ちてしまうので注意しましょう。
- 指矩の使い方は、基本自分から見て材料の奥側に指矩を当てて自分に向かって(手前)墨を付けます。ちなみに買うときは矩を見るのに商品を重ねてみて、はみでてるのは精度が悪いのでやめましょう。
- メジャーは親指で押さえる癖をつけて、巻くときは指を怪我しないように注意しましょう。測るときは斜めにならないように測りましょう。長く測れば測るほど斜めになると寸法が伸びていくので注意です。一番使う道具なので大事にね(*‘∀‘)
- 玄能はスイングの軌道を掴んで、材料を押さえる手を離し同じ振り幅で狙い打ち付けましょう。少しずつ力を加え一定リズムで叩くとブレないです。あと手首のスナップを上手く使いましょう。調子に乗ると Hitting a finger ( Д ) ゚ ゚ するので気を付けましょう。
- 手鋸は脇をしめて肘だけの振りで引いて切ることを意識して、ある程度上からの目線で作業すると上手く切れます。これはどの道具を使うときにも共通していることですが、姿勢が悪いと上手くいかないので、姿勢よく安全を常に意識して作業に取り掛かりましょう。
- 手回しは使わず充電式電動ドライバーを使いましょう。

完成までの手順
完成をイメージして寸法を決め、材料に寸法通りの墨付けをします。この時に一本の材料に対して余りを極力少なくしましょう。これができれば一人前ってくらい大事です。加工前にすべての部材を頭に入れて、余りそうな部分に細かい材料を当てはめて余すことなく材料を使いきります。最初はメモしてチェックしながらやるといいです。次に加工です。
先に長い部材から切断していきましょう。なぜかというと、もし間違えて切ってしまったときに長い材料から切断していくと間違えても代用がきく(業界用語で「逃げがきく」と言います)ためです。これは同じ材料の量であったとして、長いほうから切って、間違えたときに、間違えた材料から細かい材料をとることでトータル量を同じにする考え方でよく使います。
なので材料加工が終盤になればなるほどミスれないことになります。そして材料の切断・加工が終わってから組立していくと効率・仕上がり共にいいです。次に組立です。
組立の際に釘を使う場合、打ち込む途中で木が割れてしまうことがあります。これを防ぐには釘の先を玄能で叩いて軽くつぶすと割れを防ぐこともあります。あとは釘の長さの1/3くらいまで錐で下穴(業界用語では「バカ穴」)をあけると割れにくいです。その他には同じ木目に複数の釘を近くに打たないとかです。次に仕上げです。
これも基本中の基本ですが、材料は角が処理されておらず、直角なまま販売されています。(ツーバイ材を除く)そのためその角で怪我をする場合があるので、角処理を行います。業界用語では「面取り」と言って、材料の角の部分を45度の角度で鉋で軽く削ります。そうすることで怪我を防ぎます。
そして、ガタつきや傾き、水平などをチェックして異常が無ければ完成です!

電動工具
電動工具を使えば作業効率と加工精度が格段にアップします。高精度の家具やインテリアのリノーベーションを考えている方にはおすすめです。ただし、電動のため危険性が高まるので十分な知識が必要で、使用の際には細心の注意を払いましょう。
おすすめ電動工具
- 充電式電動ドライバー
- 電動丸ノコ
この二つの電動工具+手道具を揃えれば大抵のものは作ることができるようになります。欲を言えば、鑿(のみ)と鉋(かんな)もほしいところですが、慣れてきてからでいいとおもいます。
自分が電動工具を使うときに注意するところは、予想外のことが起きたときに電動工具がどのような挙動をするのかを予め、できるだけ予想しながら作業します。そしてその予想外が起きたときにどのようにして回避するのかまで考えておきます。それは作業が完了するまで常に頭の中に入れておきます。
そうしていくうちに慣れてくると危険予知の癖がついてきます。それと、「焦る」とか「慌てる」などといった危険予知を妨げるような考えが事故を引き起こす大きな原因だと自分は思いますので、常に冷静に作業に取り掛かることが基本であり重要なことだと今までやってきて思うところです。
その集中力が途切れると、間違えたり怪我をします。こまめに休憩を取りながらやるといいです。人間の集中力の最大継続時間は2時間と聞いたことがあり、大工の1日の作業時間にも小休止が挟まれています。
うちの場合は8:00から作業開始で、10:00~10:30で30分間の「一服」という小休止を挟み、12:00~13:00迄の昼休憩で午後からは15:00~15:30迄の小休止の「一服」を挟み、17:00で1日の作業が終了となります。

「一服」だらけじゃねーかって思う人もいるかもしれませんが、実際やってみると体力的にも精神的にも無理のない作業時間になっていると実感します。たまに作業が遅れているため一服なしで押し切るときがあるんですが、そのときは大抵間違えたりミスが多くなるので結果的に効率が悪いです。
なのでこれからDIY作業されようとしている方はこまめに休憩を取りながら楽しくやることをおすすめいたします。あと、なめてかかると必ず怪我します。これは車の運転によく似てるかなって思います。機械を人間が動かすとき、誤った使い方をすると凶器になりかねませんので軽い気持ちでやるといいことないので、やるからには真剣にです。
といいつつ自分も今までかなりやらかしてます。でも危険予知の癖は弟子入りの頃からつけさせてもらっていたので、大きな怪我や体の一部を事故で失ったというようなことは過去には一度もありません。電動工具なので待ったが効かないので、しつこいようですが十分注意していただきたいです。電動工具を取り扱ううえで一番重要視していただきたいのが今言った安全管理でございます。安全に楽しみましょう!
使い方
充電式電動ドライバーの使い方のコツとしては、ネジがある程度刺さりこむ迄しっかり指でネジを押さえるのと、進行方向に軽く押し付けながらネジの先端から力の入れ方を一直線を意識してしっかり握り締め付けることです。
電動丸ノコの使い方のコツは、切る前に、切った後迄の想像をしてから切り始めること。危ないと少しでも思ったら、すぐに作動スイッチトリガーがら指を離すこと。切る材料の下に物がないかを見ること。切る材料の両端に台を入れていないか。この両端に台というのは、材料を切るときに台の上に乗せて切るときの鉄則があります。
一枚の長い板を切るとしましょう。そのとき右利きの場合、右手に丸ノコ左手で材料を抑えるんですが、何か台の上に板を乗せて切らないと作業台も切ってしまうので台に乗せるのですが、どの台(垂木とかでもなんでもいい)を切断墨よりやや左と、同じ高さの台を左端に置き、墨より右側には板の下に台をいれずに切断すること。
なぜかというと、切り墨を真ん中にしてやや左右に台をかませて切ったときに重みでΛの字もしくは、台をかませる距離によってはVの字に板が作業台に着きます。その時に丸ノコの高速回転している刃が瞬間的に板に挟まり(業界用語で「絞られる」といいます)勢いよく自分のほうへ丸ノコが跳ね返ってきて極めて危険です。これで大抵の大工さんは怪我をします。
なので切るときは、切り墨より必ず左側にだけに台をかませ、左手で材料をしっかり押さえてから切断てください。(左利きの方は逆です)自分は経験があるので、もしこれを行っても自分で制御できますが素人には絶対できません。指を落としてから後悔しても遅いので必ずここは守ってほしいです。怪我をする原因ナンバーワンです。
機械なので自分の考えてる以外の予測不能の動きもします。その点も十分注意して作業するように心がけましょう。使い方をちゃんと知ればこんな便利なものはありません。細かな部分の施工以外は手鋸を触りたくなくなります。笑

気を付けること
自分で物を作ることはとても面白いし楽しいです。そして誰かに喜んでもらうこと、これがもっと楽しくさせます。少しずつ技術を磨き道具をそろえていけばもっと楽しくなります。安全面だけ注意すれば頭も体も使いますのでとてもいいことだと思います。興味を持たれている方は趣味として気軽に始めてもいいかと思います。
いつか今度は「大工がおすすめする電動工具メーカー」などを紹介しようかなと思っております。この記事が誰かのお役に立てると幸いです。バイビーだ!



